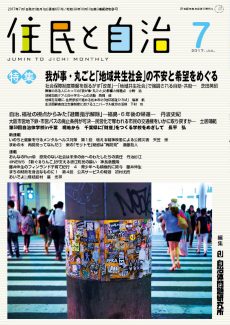
|
目次
事務局として気になった記事にコメントを載せます。一緒に読み合わせしましょう。
●特集●我が事・丸ごと「地域共生社会」の不安と希望をめぐる
県政白書を作成の皆さん、社会保障という言葉がなくなります。改めてこの言葉の意味を学習しましょう。
•社会保障制度基盤を揺るがす「改革」-「地域共生社会」で強調される自助・共助─ 芝田英昭
このたび成立した、「介護保険法等改正案」について、そこで何が目論見られているのか、丸ごと地域に投げ込むため、この改正工程で、31法案を一挙に改正しています。このやり方は、子ども子育て支援法、地方自治法の改正等々のやり方の踏襲であり、私たちがじっくり学習しないととんでもない誤謬と、障害者支援などをなくすことになりかねません。憲法の改正を地で行くものです。
•障がいのある人にとっての「我が事・丸ごと」の影響と問題点 小野 浩
今回の法案の審議が森友学園問題の中で、軽視され、非情に重要なことがなにも法律に明記されず、政令等に委任されたものになっています。立法府の怠慢であり、審議差し替えが必要です。市は今回出された共生型サービスにつても詳しく述べられ、私たちが求める共生社会について、4点にわたり述べられています。関係者の方々のご意見を求めます。
•地域包括ケアと白十字ホームの活動 西岡 修
東京都の郊外の東村山市に、白十字ホームが1967年に設立され、ボランティアを受け入れ地域との協働活動を行っています。1970年代後半には施設の社会化運動に取り組み、「わらしべ長者方式」を生みだしました。国が進める地域包括ケアシステムには、特別養護老人ホームは、枠外となっています。ボランティアに頼るケアシステムですが、最も重要なことは「人」です。「施設と地域」と言っても、共感しあう人の集まりをコーディネイトできる人材を得ることが大切です。
•地域を足場に、住民参加で進める松本市の「地区福祉ひろば」 塩原 航
地区福祉ひろばは1992年に松本市独自の事業として生まれ、福祉拠点として、「高齢者福祉」の枠を超えて、「地域づくり」へ発展していきました。福祉とは住民の幸せのこと」という単純な言葉で表現されています。一方筆者は「行政福祉」と「地域福祉」の関係を問うておられます。あなたならどう思いますか。
•生活困窮者自立支援制度におけるユニバーサル就労の活用 下村 功
2015年4月から施行された、生活困窮者自立支援制度のなかで、中間的就労」(ユニバーサル就労)について具体的な報告されています。生活困窮者一人一人に寄り添った支援の必要性と、受け入れる企業・団体の普及そして「その後」のステップアップを説いておられます。この課題と、生活保護制度との関係に私は?でした。
•自治、福祉の視点からみた「避難指示解除」─福島・6年後の帰還─ 丹波史紀
2017年4月は、福島の被災者・自治体にとって大きな課題の提起がされました。あれから6年がたち、今避難解除指示を出した政府は、責任ある役割を果たしているのでしょうか。住民の生活再建をどう保障するのでしょうか、小規模事業者にとって生計が保証されるのでしょうか、自然からの脅威が生まれていますが、いまだ帰還に同意できない住民のことを考えているのでしょうか。帰還政策が先行して、役場機能が入りはしましたが、住宅問題をはじめ福祉制度の行政事務はどこが担うのか、模索中です。地方自治が根底から覆され、ゼロからの出発となっている現状からの復興を私たちも支援していきたいものです。
•大阪市営地下鉄・市営バスの廃止条例が可決─民営化で奪われる市民の交通権をいかに取り戻すか─ 土居靖範
2018年4月から大阪市の公共交通が、民営化されます。採算が取れなく手のものではなく、悪質な詐欺として行われています。生活と基本的人権を地域で守るため、交通権保障が重要だと筆者は訴えています。広島自治研でも、『移動制約者と地域交通』という本を出していますので参考にしてください。
•第59回自治体学校in千葉 現地から 千葉県に「財産」をつくる学校を目指して 長平 弘
•書評 相川俊英 著 『地方議会を再生する』 坂本 誠
•書評 関耕平ほか著 『農山村地域と鉄道の役割に光をあてる─「三江線の過去・現在・未来」に学ぶ─』 佐々木忠
三江線ということで、広島県民には、身近な問題を扱っている。広島自治研の月報でも、398号・401号で取り上げています。ぜひ併せお読みください。
•書評 にいがた自治体研究所 編集・発行『県民は、なぜ米山知事を選んだのか 新しい市民政治への期待と展望』 池田 豊
●連載●
•おんなのRun㊿原発のない社会は未来の命へのわたしたちの責任 丹治杉江
原発の被害は、広島での被害と同じような歴史をたどっていますが、3.17前橋地裁判決で、「津波の予見可能性があったのに東電は安全性よりも経済性を優先。国は東電の姿勢に対し規制責任を果たしさなかった」と、画期的な人災と認めています。この行くへを見守りたいものです。
•@NEWS 「新ぐるりんこ」が支える浪江町民の願い 神長倉豊隆
原発で避難させられ、このたび避難指示解除区域、居住制限区域が解除され帰還ができるようになったが、多くは高齢者だと、地域にとって、移動手段をNPO が守ろうとしています。要求を基の活動をいつまでも続けてほしいものです。
•まちの財政を身近なものに!第4回 公共サービスの財源 初村尤而
•藤井伸生のフィンランド子育て紀行4 青少年へも積極的に関与 藤井伸生
社会福祉の進んだ国、今回は青少年ネウバラを紹介しています。捜索隊・若者の家があり、役所的でなくて気軽にいられる」スタッフは、「その人の存在を認めてあげ、真正面から向き合う」とか。
•新連
•まめの木 再開発ってなんだ①東の「モリトモ」疑惑は“再開発” 遠藤哲人
•いのちと健康を守るメンタルヘルス対策 第1回 増える精神疾患による公務災害 天笠 崇
広島県職員の中にも多くのメンタルヘルスに悩んでいる休職者がおられます。これから一緒に学習していきましょう。
•ローカル・ネットワーク
•第59回自治体学校in千葉 現地から 千葉県に「財産」をつくる学校を目指して 長平 弘
•Jつうしん
•史跡さんぽ㉕
•おいでよ17 檜枝岐村
•編集後記
|