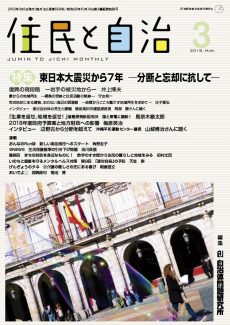
|
目次
事務局として気になった記事にコメントを載せます。一緒に読み合わせしましょう。
●特集● 東日本大震災から7年 ―分断と忘却に抗して―
7回目を迎えるこの年、メディアの報告が、かってに比して低い状況です。改めて、読んで支援の在り方を考えましょう。
•復興の現段階 ―岩手の被災地から― 井上博夫
津波災害で、市街地すべてが被災し全く別の高台にまちづくりを行う復興の足取りは大変なものがある。岩手県での取り組みの報告を読んで、厳しいものがあったと、この復興の中で、中学生・高校生などの活動が目を楽しませてくれました。
•農からの地域再生 ―福島の奇跡と住民活動の軌跡― 守友裕一
農耕地の再開には、多分多くの歳月が必要であろうと思って居ましたが、ここ福島では、非情な哲学者の農家の人々によって、放射能に対する農地での分解作業が克明に明らかにされ、カリュウム投入することでの対策が、「福島の奇跡」として生まれています。前を向いている福島の人たちは深く傷ついた人たちだからこそできることがあった、大地に根差した着実な歩みを起こされてきたとの報告です。
•荒浜地区にある建物、本のない海辺の図書館 ―故郷からこころ離さず地域再生を求めて― 庄子隆弘
津波により、何もかも流されてはきたが、そこには何かしら生きものが住んでいる、新たな発見が、図書館を思わせています。そこに集い、交流することで幅広くなる、図書館の役割を言い当てていますね。この取り組みもウエブサイトで見てください。「ARAHAMA・BLEND」
•インタビュー 被災自治体の再生と課題 陸前高田市建設部部長 阿部 勝さんに聞く 阿部 勝
このインタビューのキーワードを挙げてみます。震災被害の3本の柱・7年間のまちづくり・市民協働の力・地域コミュニティーの強さ・防災集団移転促進事業・12.5mの防潮堤・祈念公園・震災遺構・技術系職員・集合住宅でのコミュニティーづくり・市民生活に必要な拠点・地域経済の循環・持続可能な自治体・と挙げていますが、普通の生活を取り戻すことに視点を置いた仕事が大事だと語っておられます。
•「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟判決 国と東電に勝訴! 馬奈木厳太郎
2017年10月10日、福島地裁において、『生業を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟の判決がいい渡され、国と東電の法的責任を認めた大きな意義があります。これまで国と東電は「津波は想定外だった」と主張してきたものをこの判決は明確に否定しました。安全性より経済的利益を優先させる姿勢に警鐘を鳴らす判決です。新たな展開を期待したいものです。
•書評 上原公子・小川ひろみ・窪田之喜・田中 隆 編著 『国立景観裁判 ・ドキュメント17年―私は「上原公子」―』 白藤博行
住民訴訟が住民自治・市民自治を攻撃する手段として使われてしまったという事実と、環境問題での新たな、景観権・景観利益の保護の闘いの総括を行っています。これからの運動の参考になると思います。
•2018年度政府予算案と地方財政への影響 梅原英治
安倍暴走内閣の予算は、まさに管理人のいない野焼きの暴走火炎のごとく、数々の木々を燃やし続け、防衛予算突出の姿を現し、国民生活を破壊しています。憲法改悪に向け、経済界・富裕層優遇の格差拡大予算ですね。国際的にも批判を浴びる国際観光旅客税を徴収し、内閣・内閣府拡大をだしているとは、もはや一日でも早くやめさせなければ、日本国は滅びてしまいます。しかし、この予算を最大限活用しているのが、広島県・広島市です。
•インタビュー 辺野古から分断を超えて 沖縄平和運動センター議長 山城博治さんに聞く 山城博治
沖縄闘争の先駆者の、この戦いでの姿勢に触れ、改めて連帯の気持ちを持ちました。皆さんも共有して沖縄の闘いを続けていきましょう。
●連載●
•おんなのRun58 新しい南足柄市へのスタート 角野圭子
小田原市と南足柄市の合併反対の取り組みの報告です。よくわからないうちに合併を押しだす当局に対し、広報活動をひろげ、署名を集める活動は大変なものがあったことでしょう。今後の監視を強めてください。
•@NEWS 生活保護基準の引き下げ問題 田川英信
この報告は基本的問題を数々提起されています。改めてこの制度の欠陥を追求し改善して、生活保障としての基準を確保してほしいものです。国民すべての地盤ですね。c
•げんぎょうのタネ ③介護の難しさの先にある喜び 朝倉啓文
愛知県の特別養護老人ホームでの介護について、普通の生活とは、ひとつひとつの動作の支援と、残存機能の維持管理に目を配る支援、が行われています。大変だと思いますがよろしくお願いいたします。
•最終回 まちの財政を身近なものに! 数字のすき間から住民の暮らしと地域をみる 初村尤而
財政の分析を行うとき、研究・調査と運動とを一体のものとして進めなければならないという研究のスタイルを再度確認されています。守口市の図書館の効果測定や、高槻市の市バス無料化の検証で、庶民の生活を重層的に分析し、社会参加効果、健康増進効果・経済効果・環境負荷低減効果など、バス無料化での4つの効果が挙げられています。図書館の貸し出し密度を評価する、経済的理由による交通弱者は作り出さない地域になっているなどの評価が行われています。他都市との比べ合いではなく、人など、個別での庶民と行政とのつながりを求める分析活動が必要だと思いました。
•いのちと健康を守るメンタルヘルス対策 第9回 「過労自殺」の予防 天笠 崇
過労自殺の根絶には、この精神医学的意見書の分析が実施されなければいけません。労働者全員のメンタルヘルスの実施と職場ハラスメントの撲滅が重要だと思います。自分たちの環境をどう作り出すか、働きかけるかの知恵を私たち自身が身につけておかなければいけないと思います。
・Jつうしん
•史跡さんぽ33
•ローカル・ネットワーク
•おいでよ25 西興部村 菊池 博
•編集後記
|