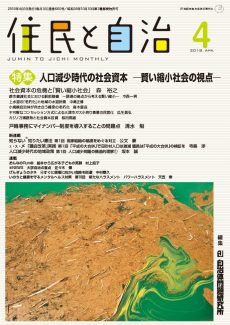
|
目 次
事務局として気になった記事にコメントを載せます。一緒に読み合わせしましょう。
●特集● 人口減少時代の社会資本 ―賢い縮小社会の視点―
•社会資本の危機と「賢い縮小社会」 森 裕之
日本の不動産はいくらあるのでしょうか、これらが近年社会資本の縮小に収れんさせられています。それはなぜか、社会資本の老朽化、財政ひっぱく、人口減少・高齢化に対応するためだと言われています。この③要素を確認し、地域での話し合いをじっくり行い賢い縮小策を、地方自治体は進めなければ、個人の基本的人権や地域コミュニティーの破壊につながりかねません。広島県・広島市はこれら社会資本を民間に移管し、責任を回避する施策を推し進めています。
•都市縮減社会における駅前整備 ―誘導の拠点から考える賢い縮小― 今西一男
現在広島市の駅前再開発は終了しているように思いますが、この整備が今後の縮小社会資本整備の目標に合っているかと考えた時、この高層ビル群がもたらす負の財産として、自治体への負担を危惧します。なぜなら、この再開発は、単に利潤追求のためや、州都のシンボルとして、意味もなく位置づけられ、単なる「にぎわい」を引き出すにすぎないと思うからです。この記事で駅前再開発の基本を見直す考え方の新たな視点を手に入れ考えてみましょう。
•上水道の「老朽化」と地域の水道計画 中島正博
水道法第1条に、『正常にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的』とあります。このことを念頭に、水道事業の更新を見つめていきたいと思います。広島県では、広域水道事業を民間へ払い下げていますが、この検証をすることが必要です。
•小規模自治体が向き合う橋梁の老朽化 高木直良
小規模自治体が管理する橋梁の点検が、話題となりますが、そもそも橋梁や道路などのようにネットワークを形成するために作られたものを、単一の自治体に責任を押し付けることがどう課と思っています。作る時の実施計画書には箱のもの補修計画が部位ごとに記述されおり、これの実施がなくては正常な維持管理ができないことは最初から明白です。これらを行わない社会風潮は、社会資本の建設は、老朽化したら建て替えればいいとの前提があったからに外ありません。国土交通省が「社会資本メンテナンス、元年」と2013年に位置付け維持補修の交付金制度を立ち上げましたが、全国の個別自治体に対する財政的支援を位置付けましたが、この作業を技術的にも財政的にも安定的に確立するためには、一地方公共団体が行うのではなく、専門職員を持った県が主体的に行うべきではないでしょうか。考えてみてください。
•不可解なコンセッション方式による大津市ガス小売り事業の民営化 瓜生昌弘
広島ではガス事業は長く民間が行っており、これが全国的には、公営があるということに初めて気づきました。公共施設等運営権制度という便利な民間委託準備制度が考えられたようです。改めて社会資本の在り方を考えさせられました。
•カジノ万博誘致と社会資本投資 桜田照雄
少子高齢化に向かう中、社会資本整備費の社会配分機能が細くなるとの危機感から、カジノ産業を誘導しようと生まれたとか。その時、経済効果のみを示し、「費用便益分析」である、依存症対策費や罹患可能性とその経済的損失など、庶民の一番心配することを抜きに行うとは、怒ります。改めて社会資本投資の果たす役割を、学びました。
•書評 社会教育・生涯学習研究所 監修 岡庭一雄・細山 俊男・辻 浩 編著 『自治が育つ学びと協働 南信州・阿智村』 岡田知弘
ぜひこの本を読んでください。広島自治研では15冊販売しました。
•書評 木佐茂男 監修 原田晃樹・杉岡秀紀 編著 『合併しなかった自治体の実際 非合併小規模自治体の現在と未来』 榊原秀訓
•戸籍事務にマイナンバー制度を導入することの問題点 清水 勉
政府が戸籍までマイナンバーを活用しようと策動していたことが語られています。個人情報の考え方をもう一度確認してください。中国では顔認証が進んでいるとか。
•福島県 帰還が始まった原発避難自治体の現状と課題 角田英昭
公の帰還問題と個人として故郷の思いの間には、大きな意識格差が出てくることでしょうが、7年間という年月はそれをさらに複雑化させていることでしょう。
●新連載●
•知らない☆知りたい憲法 第1回 国家組織の基礎をめぐる対立 公文 豪
•ス・ス・メ「議会改革」実践 第1回 「平成の大合併」で旧町村人口は激減 議員は「平成の大合併」の検証を 寺島 渉
憲法の学習が再開され、130年前の自由民権思想家の植木枝盛が説いた国家組織の基礎が語られ学びました。国の在り方を考えるとき、個人と家族のどちらに基礎をおくかがこんなにも大きな問題であるということを知りました。現憲法の個人主義の考えを再確認しました。
•人口減少時代の地域政策 第1回 人口減少問題の構造的理解① 坂本 誠
人口動態の科学的分析で、なぜこのような現象が起きているのかをつかむことが大切なのだと学びました。まずは、自然増減と社会増減を基礎的データとして活用し分析することから始めなければいけませんね。
●連載●
•おんなのRun59 絵本から広がる子どもの笑顔 村上招子
執筆者は広島県三原市の保育士さんです。子どもに読み聞かせの経験を語られています。
•@NEWS 大学自治の盲点 佐々木 彈
多くの大学の人事部に文科省の高齢者が入って支配し、有期雇用制度を蛇足的に行っていたとは。・・・・大学の自治も滅びますね。
•げんぎょうのタネ ④すぐに現場に向かい危険を回避 中村泰久
今回初めて、このコーナーでは豊橋市の現業職員の方々の生の声が聴かれていることを知りました。本当に市民の生活を良くするために、全霊を使って作業をされている姿に感動しました。
•いのちと健康を守るメンタルヘルス対策 第10回 新たなハラスメント パワーハラスメント 天笠 崇
パワハラには6類型があることを知りました。①暴行・傷害・②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言・③隔離・仲間はずし・無視・④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害・⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと、⑥私的なことに過度に立ち入ることで、増加傾向にあると・・・・
•Jつうしん
•史跡さんぽ34
•編集後記

(書評 岡田先生.pdf)
2653687バイト |
|