| |
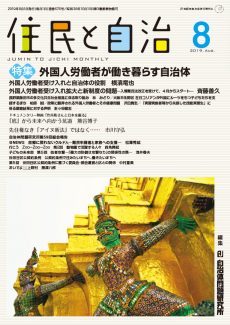
|
目次
事務局として気になった記事にコメントを載せます。一緒に読み合わせしましょう.。あなたの感想や意見もお寄せください。
●特集● 外国人労働者が働き暮らす自治体
広島県には、2017年10月末時点で、外国人労働者数は28,358人で、全国で第12位にもなり、多くのが労働者がいますが、この人たちについて、考えてみましょう。
•外国人労働者受け入れと自治体の役割 横濱竜也
基本的な課題である、外国人労働者を受け入れることに対し、彼らに対する、自己責任がないことを前提にすると、受け入れる3つの理由として、①貧困から逃れるためにやってきた「経済難民」であること、②受け入れ国は、一定の便益を受けていること。③「余所者」扱いできない社会人であること。が掲げられています。このことを改めて確認したいと思います。
•外国人労働者受け入れ拡大と新制度の問題─入管難民法改正を受けて、4月からスタート─ 斉藤善久
2018年12月8日、我が国の外国人労働政策を大転換する出入国管理及び難民認定法改正が成立し、2019年4月1日に施行されました。この改正の審議で、外国人技能実習生として、いわば裏口からの受け入れを行ってきたことに対し、外国人労働者の権利が著しく阻害されていることが明らかにされました。しかし、この改善が大きな課題だったのですが、移民政策ではないとしながら、特定技能制度の拡大で、より多くの外国労働者を多く集めるものに設計されたものにすぎません。外国人労働者の職業選択の自由・転職の自由・退職の自由の拡大が、言葉上だけいなく、実際に出来るよう制約を改正することを明記させ、制度改正を追求していきましょう。
•長野県飯田市の多文化共生社会推進に係る取り組み 林 みどり
長野県飯田市での外国人の地域への受け入れ態勢の経過が述べられています。今日の経済情勢の変化が、中国人からベトナムに移った時期などが明らかになるとともに、一自治体が抱える多文化共生社会の熟成にも、大きな力が必要であることが分かります。言語の共有化が最初から出てくるあたり、この課題での日本語での意思疎通の難点が見れます。ボランティア活動に依拠するのではなく、自治体として取り組む必要性をもっと訴えてほしいものです。
•大阪市生野区 在日コリアンが外国にルーツをもつ子どもたちを支援するまち 柏原 誠
外国の人たちが集住する地区として、北海道占冠村、の外国人比率が22.69%と一番高く、大阪市生野区が21.78%で全国2位です。ここの大正時代からの歴史の中で、朝鮮人の方々が1世から3世と有数の在日コリアンのコミュニティが産まれています。ここでの子どもの学習支援DO・YA、体験活動DO/COを現場から「多文化共生」の課題を見ています。また政府の外国人施策の問題点として、日本の植民地支配にもかかわるオールドカマーの存在が等閑視されている。すでに在日外国人270万人の半数以上は定住・永住資格を持ち、制限なく働き、家族を経営し子孫を残しています。これらの状況はすでに、国際通念上の移民です。真の多文化共生を実現するには基本法の制度とマジョリティーの意識変化が必要です。また自治体の運営において、外国人に地方参政権が必要ではないでしょうか。
•政策に翻弄される外国人労働者とその健康問題 沢田貴志
経済的に貧困な状態で放置されている外国人の方々の健康問題にスポットを当ててこの間の結核の流行から推移を見ています。このような病気が産まれる情勢の変化は、所得の高い国からの労働者から所得の低い国のからの労働者の増加が指摘されており日本社会に直面する3つの課題を挙げています。1つは、地域の医療や福祉の混乱、2つ目は、日本社会全体の労働条件の引き下げ、3つ目は、日本企業が国際的なスタンダードから取り残される等を挙げています。
•「実習実施者等から失踪した技能実習生」に係る調査結果に対する声明 針ヶ谷健志
弁護士さんから法律に対する詳細な説明が行われています。言葉の定義などこれを最初に読んでいきましょう。またこの法律に対する説明を行った法務省の考え方に厳しい疑問を示されています。この法律が動きだす中で、外国人労働者の実態を、より具体的につかむことが求められます。
•ドキュメンタリー映画『作兵衛さんと日本を掘る』「底」から未来へ向かう坑道 熊谷博子
2011年5月25日に、山本作兵衛さんが描いた(筑豊炭田で幼いころ働いた、生粋の炭鉱夫。自らが体験した労働や暮らしを子や孫に伝えたいと、60代も半ば過ぎから、本格的に絵筆を執り2000枚も書きあげた)ものが、日本最初のユネスコ世界記憶遺産に登録されました。作兵衛さんが描いた中でのおんな鉱夫のカヤノさんの姿は、働く誇りを表しますが、炭鉱閉山と原発開発の歴史的すれ違いに怒りを感じます。
•先住権なき「アイヌ新法」ではなく…… 市川守弘
2019年4月、国会はアイヌ新法を成立させましたが、この法理の持つ根本的な問題点として、アイヌ文化の理解がない点、アイヌのコタンに代わる現実を見ない点、先住民族に対する世界の動きを参考にしない点など、本当に愚かなものだと思いました。明治政府が行った150年間の施策を本当に反省しなおすことが、まずは出発点ではないでしょうか。私たちもこの問題にもっと関心を持って行こうではありませんか。アメリカでインデアン再組織法など参考にすべき法律があります。
•自治体問題研究所第59回総会報告
全国自治研の活動状況とこれからに取り組みが間接に述べられ地ます。ことは、昨年度を上回る42団体からメッセージ・祝電がありました。またとっと英、高山のまちづくりの結集も報告されました。
●連載●
•@NEWS 故郷に戻れないクルド人─難民申請者と家族への支援─ 松澤秀延
世界の難民問題で、日本にもクルド人の方々が今難民申請をしているとのこと、かららはトルコからの難民で、難民と認定された人は一人もいないとのことです。彼らは仮放免という不安定な立場で、無権利な状態で、2000人を超えて、多くが埼玉県川口市、蕨氏に在住しています。クルドを知る会がボランティアで支援活動をしているようです。
•行こう Zoo-Zoo-Zoo 第2回 動物園で活躍する人々 森角興起
動物園で働く人は、何かと兼務で忙しい飼育員で、就職するために資格は特に必要ないそうです。職員以外で動物園を盛り上げる重要な役割は、ボランティアの人たちなのです。海外では先進的な動物園では、教育専門スタッフ、研究所で教授制をとって複数の研究室を設けているところもあるのです。毎年小人数しか採用されず厳しい状況のようです。
•子どもの未来図 第5回 他者攻撃─「最大の防御は攻撃なり」の関係性の罠─ 浅井春夫
今回はいじめの本質について述べて今う。この問題の最初の事件として、1986年2月に起きた経過が述べられています。おいじめの3要素、①「力関係のアンバランスとその乱用」②「被害性の存在」③「継続性ないしは反復性」を挙げています。また、いじめの3つの段階として、①「孤立化」②「無力化」③「透明化」に分けて説明されています。「ストレスフルな学校環境」を放置したままで、教え込み主義の「道徳」でいじめが解消されるわけでなく、一層大人に従順な子どもを作ることが進められています。いじめを生み出す「社会構造」「学校公像」「地域構造」の実態を把握することが今問われております。
•世田谷区公契約条例 公契約条例で住みたいまちへ、働きたいまちへ 第5回 世田谷区公契約条例に基づく委員会・部会運営と区との関係 中村重美
公契約条例の施行により、世田谷区でのこの運営は、条例によって、設置要領が定められこれに基づき運営が行われることが議事録の公開等で、同懇談会で明らかにされ改善が出来ました。またチェックシートの文言についても、条例の趣旨の説明や、報告事項の検証など条例の実効性を担保として、議論を積み重ねることが出来たようです。
•おいでよ41 上野村 黒澤八郎
•Jつうしん
•史跡さんぽ50
•編集後記
|