| �@ |
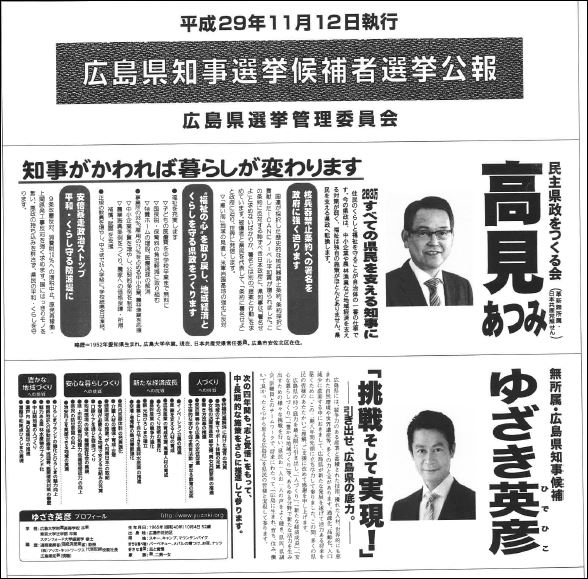
| �L�����̎����̖̂����Ƃ͉����A�����Ƃ͌o�ϐ����݂̂� |
|
�@1�P���P�Q���L�����m���I�����A���[���R�P.0�X���ŁA�O����O�D�W�W�������A�����ł������������匧����������o�����������́A71,353�[�A���[��9.9.�����l�����܂����B
2017�L�����������̓ǂݒ�����
�@���̑I����ŁA���������̃p���t�́A�u2017�L�����������v���Q�l�ɁA�u283�������̊肢�ɓ����錧���v�̎����ցA�Ƃ܂Ƃ߂Ă��܂��B
�O�̓]��
�@�@�j����֎~���ւ̏����𐭕{�ɂ��܂�m���ցA
�@�A������ƁE�_�ыƁE�n��Y�Ƃ��x�����A�������[������m���ցA
�@�B�����10���ւ̑��Œ��~�A9�������X�g�b�v�A���{�\�������Ɂu���\���v�m���ցA
�@���X���[�K���ɁA45���ڂ̋�̓I�ȗv������������A��������܂����B�����ł̌��e��32���ڂɂ��Ę_���Ă���A���߂ēǂݕԂ��Ă��������B
�Z������ł̒m���I��
�@���I���ƘA���Ƃ����Z���Ԃ̑I���̂��߁A�\���Ȑ��|�����o���Ȃ����ł̑I���ł͂���܂������A���������E����Ɛ��������A���Ƃ�ό��Y�ƁE�ꕔ�̌��C�Ȑl��Ώۂɂ����L���Ȏ{�����f���Ă�������m�����A���ꂩ��4�N�Ԉ��������L�������̂��������s�����ƂɂȂ�A����܂ł̌����̊i���ƕn���̔�Q�ɂ��āA�������͐���傫���グ�Ă����K�v������܂��B
�L�������̏��@
�@�܂��A���{���t�̒n����������́A�����̌��Ƃ������ԋ@�ւ�p�~���āA���B���ւ̓����X�g���[�g�ɍs�����Ƃ��ł����A�L���s�╟�R�s�̑�s�s�𒆐��s�s�Ƃ����ӎs���Ƃ̘A�g�g�ɑI���ƏW��������s���A�L�������Ɋi����ł��Ă���A���茧�m���͂��̕��j�̐��i�҂ł���A�{���̌��̖��������������A�ق�̈ꕔ�������@�\�����Ȃ����m���Ɏ��܂����̂ł��B
�Z�������̐i���E���W
�@�������A�Z�������A�c�̎����̊����́A�S���e�n�Ő��̍L���������ĂыN����A�s���ƌ��̖����́A�A�g�����Ȃ���A����S�̂Ƃ��Ĉ��肵�����W��]��ł��܂��B��s�s���S�̐���ł͂Ȃ��A�����ȏZ�������̉^�c����b�ɂ����n��Љ�Â��肪�A���ꂩ��̎Љ�i���̕����ł���A�n��z�^�o�ς̎�@�𑁂��g�ɒ����邱�Ƃ��]�܂�Ă��܂��B
�����������̐i�W��
�@���ہA���A��ÁA����A�����̎{��̐��i�ɂ́A�Z�������g�D�̘A�g�E�����Ɣ��W���K�v�ł����A�Z���̒n�������ɑ���l���̔��W���������Ȃ����̂ł��B����Ƃ��������̒n�����������̊�b�ł���u�Z�������v���L�߂Ă����܂��傤�B
|